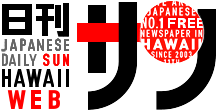【高尾義彦のニュースコラム】世界の人口 日本の少子化を考える
インドが中国を抜いて世界一の人口大国になるという。国連発表を聞いて、改めて世界の人口問題や日本が直面する少子化の課題を考えさせられた。世界の人口は当面増え続けるが、ある段階で下り坂になる時期を迎えるという観測もあり、水も資源も有限なこの地球上で、人類にはどんな未来が想定されるのか、気になる問題だ。
世界人口デーの7月11日に発表された国連人口基金(UNFPA)のデータによると、世界の総人口は79億5400万人。中国が14億4850万人、2位のインドが14億600万人で、2027年にはインドが中国を抜くという(来年という推計も公表されている)。世界の人口は2080年には104億人に達すると推計されている。
現在、人口1億人を超えている国は、アメリカ、インドネシア、パキスタンなど14か国あって、日本は1億2560万人で11番目。日本の人口は2008年にピークを迎え、その後は減少傾向を続け、「少子化」が大きな問題となっている。
筆者が生まれた1945年は、第二次世界大戦の敗戦の混乱期で、出生数は190万2千人だった。47年から49年にかけての第一次ベビーブームの時代は年間260万人台を記録し、いまこの年代が70歳台に達して高齢化社会の〝主役″となっている。
筆者は出生数が少ない世代だったため、進学や就職の機会には、相対的に恵まれたと感じているが、最近の出生数はその数字にも及ばない。第二次ベビーブーム(71~74年)には年間200万人台だったが、2016年に100万人を切り、その後も減少傾向が続く。
合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子供の平均数)は21年のデータで1.30まで落ち込み、回復の気配はない。国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2053年には総人口が1億人を切って9924万人になる。高齢化も深刻で、敬老の日に合わせて厚生労働省が明らかにした数字では、100歳以上の人口が初めて9万人を超え、このうち女性が8万161人と大半を占めている。
間もなく人口がインドに抜かれる中国では、1979年に導入された「一人っ子政策」が少子化の大きな要因となった。戦後の49年以降、中国の人口は急増し、食糧難を懸念する政府が、出産する子供の人数を一人にする強制的な政策をとった。これが失敗だったことを認めて、2016年にこの政策を撤廃したが、人口は増えず、2021年の出生数は1062万人と史上最低となっている。
中国政府は21年5月に「3人目」の出産も認める方針を打ち出したが、それでも出生数は増えない。親の世代が一人っ子として成長し不具合を感じていないほか、子育てのための教育投資や都市部での住宅費に巨額の費用がかかり、簡単には「産めよ増やせよ」の機運は盛り上がらない。
翻ってインドの現状をみると、人口の50%以上が25歳未満であるという「若い国」としての特徴があり、女性一人の出産数は2.72人と高い数値を示す。社会的インフラが整い、寿命が延び、新生児の死亡率が減少したことが背景にある。まだまだ貧困層も多いため、子供が「労働資源」として期待されている側面も指摘される。
少子化の問題を考えるうえで、世界各地の特派員らが現地の情報を報告した『世界少子化考』(毎日新聞出版)が興味深く、参考になった。最初に取り上げられているのは韓国で、合計特殊出生率が2021年に世界最低水準の0.81を記録し、日本以上に大きな問題になっている。
韓国の場合、男性は2年前後の兵役期間を考えると就職年齢が20歳台半ばになり、結婚年齢も日本などより遅くなる。儒教思想を重んじる韓国では、結婚する場合、男性が住居を用意することが多いが、都市部の住宅が高騰して若い男性には高いハードルになる。さらに日本以上の学歴社会となって、名門大学などに子弟を進学させるための経済的負担が過大となり、一人以上の子供を持つ余裕がなくなっているという。都市部への人口集中がさまざまなひずみを生み、少子化に拍車をかけているようだ。
一方で高い人口増を続けているのがイスラエルだ。合計特殊出生率3.01は世界のトップクラス。好調な経済成長のほか、人口の4分の3を占めるユダヤ人が世界に離散させられた歴史的体験から、大家族にこだわる潜在意識が働いているという。
日本がお手本とすべき国の一つがフランスだろう。国の手厚い経済的支援だけでなく、個人を尊重し、結婚と出産の法的位置づけを柔軟にとらえて、同性愛なども含め全ての女性がそれぞれの形で子供を持つ希望を実現させる道を、法的に開いてきた。
コラム執筆中に宮城県の村井嘉浩知事が「“孫休暇”を取る」と宣言したニュースを聞いた。育児休暇を一歩進めて職員の〝孫休暇″を制度化する意気込みには賛否の声が上がったが、政府や地方自治体が、子供を産み育てやすくする環境づくりに力を入れることが欠かせない。その場合、国家としての政策優先ではなく、様々な形で幸福を求める個人を尊重する視点からの選択肢を出来るだけ多く用意できる試みを期待したい。


高尾義彦 (たかお・よしひこ)
1945年、徳島県生まれ。東大文卒。69年毎日新聞入社。社会部在籍が長く、東京本社代表室長、常勤監査役、日本新聞インキ社長など歴任。著書は『陽気なピエロたちー田中角栄幻想の現場検証』『中坊公平の追いつめる』『中坊公平の修羅に入る』など。俳句・雑文集『無償の愛をつぶやくⅠ、Ⅱ、Ⅲ』を自費出版。
(日刊サン 2022.10.12)