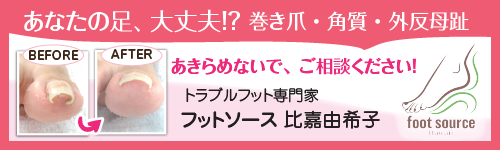みなさんもきっと、いつまでも心に残る映画の一場面をお持ちではないでしょうか。わたしは何といっても1965年のハリウッド映画「ドクトル・ジバコ」の最終場面を思い出します。
旧ソ連の水力発電所で、主人公のジバコとララの忘れ形見であろう娘が、ひょいと肩にかついだ民族楽器バラライカの弦がわずかに鳴ります。それに気づいたソ連軍幹部のジバコの兄が、はっとして「君はバラライカを弾けるのか?」と尋ねます。恋人らしき青年が「彼女はプロ並みです」と答え、叔父は「そうか、血筋だな」と言って二人を見送る。そこに主題曲のメロディーがタイトルバックに重なって流れる、なんとも印象的な終幕でした。
エルビス・プレスリー主演の1961年の青春映画「ブルー・ハワイ」と聞けば、「The night is young. And so are we, so are we.」(まだ宵の口さ。同じくぼくらも若い)という甘い歌声が蘇ります。蒼(あお)い空と海に響くスチールギターやウクレレは、ハワイの音楽に欠かせない楽器ですね。
第二次大戦直後のウィーンを舞台にした、1949年制作、オーソン・ウェルズ、ジョゼフ・コットン主演のサスペンス映画「第三の男」。息詰まる地下水道での追撃戦。光と影が織りなす映像美とともに、当時ウィーンの酒場で流行ったというチターが奏でるBGMが全編に流れ、「第三の男」というと、誰もが哀愁に満ちたメロディーを思い出したものでした。
考えてみれば、名画は名曲に支えられて、初めて名画になるのでしょう。映画音楽には民族楽器がよく使われて、エキゾチックな雰囲気を醸(かも)し出すのにひと役買ったのですが、それにとどまらず、個性豊かな民族楽器がどれほどそれぞれの国の人々の文化と暮らしに溶け込んで、深く根づいてきたことか。今さらながら、感慨を覚えざるをえません。
学生時代、南インドの古典舞踊「バラタナティアム」を鑑賞する機会があり、古代神話に由来するその優美な踊りとともに、笛や弦楽器のシタール、それにタブラと呼ばれる小太鼓の乾いた響きに魅了されました。伝説のシタール奏者ラヴィ・シャンカールの紡(つむ)ぐ音楽に、あのビートルズが深く傾倒したことはよく知られています。わたしもたまに、インドの古典音楽の演奏をCDなどで聴き、なんとも壮大で深遠な大宇宙の鼓動に身をゆだねます。
中国の二胡(にこ)、奄美大島など南西諸島、沖縄で伝えられてきた三線(さんしん)や三味線(じゃみせん)、カリブ海の島々のドラム缶からつくられた「スティールパン」、アルゼンチンタンゴに欠かせない蛇腹(じゃばら)の「バンドネオン」……人間はなんと多様な楽器を生み出し、民族固有の音楽を慈(いつく)しんできたことでしょうか。
幼いころ、母が枕元でよく歌ってくれた「ねんねんころりよ おころりよ」の子守歌には、「里のみやげに何もろた でんでん太鼓に笙(しょう)の笛」という一節があります。これらも日本古来の民族楽器でしょうが、土産にそんなものをくれる里があるものかねと、ひねくれて可愛げのない子どもだったわたしは、ずっと思っていました。
史上最悪の原発事故を起こしたチョルノーブリ(旧名チェルノブイリ)から2.5キロメートルの地に生まれた、ウクライナ人のグジー・カテリーナさん。数少ない伝統の民俗楽器バンドゥーラのプロの奏者で、17年前に日本人と結婚し、第二のふるさとになった日本で暮らしています。
12世紀のキエフ公国時代に起源を持つバンドゥーラは、50―60本の弦を持ち、5オクターブの音階を奏でられ、日本の琵琶法師(びわほうし)と同様、おもに目の不自由な人たちによって守られ、伝えられてきたのでした。
昨年4月には、夜の姫路城をバックにカテリーナさんが美しい声で歌い、パンドゥーラを奏でた「翼をください」の演奏は、大きな感動を呼びました。
「ウクライナでは多くの人々が助けを求めている。今こそウクライナの歌を伝えるべきだ」という母親に励まされ、彼女は日本全国で演奏活動を続けています。ウクライナ戦争から1年以上が経つというのに、戦火はおさまるどころか、春にはウクライナとロシア双方がいちだんと攻勢を強めるのではないか、という予測があり、バンドゥーラに寄せる思いはいっそう募ります。
えっ、わたしですか? 情けないことに、吹ける楽器といえば「法螺(ほら)」くらいです。失礼しました。


(日刊サン 2023.3.10)


木村伊量 (きむら・ただかず)
1953年、香川県生まれ。朝日新聞社入社。米コロンビア大学東アジア研究所客員研究員、ワシントン特派員、論説委員、政治部長、東京本社編集局長、ヨーロッパ総局長などを経て、2012年に代表取締役社長に就任。退任後は英国セインズベリー日本藝術研究所シニア・フェローをつとめた後、2017年から国際医療福祉大学・大学院で近現代文明論などを講じる。2014年、英国エリザベス女王から大英帝国名誉勲章(CBE)を受章。共著に「湾岸戦争と日本」「公共政策とメディア」など。大のハワイ好きで、これまで10回以上は訪問。