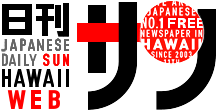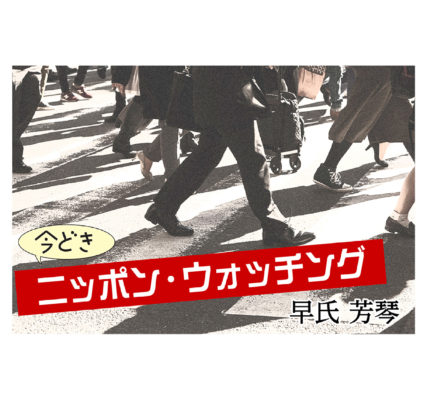日本の地方大学で、超小型人工衛星の作製に強い関心を抱き、将来宇宙開発を目指す学生が、増えているようである。彼らが作製した手のひらサイズの超小型人工衛星が相次いで宇宙へ飛び出している。機能は限られているが、低コストで、設計から開発、運用まで手軽に自分達で出来るということで、楽しみながら超小型の人工衛星の作製に夢中で取り組んでいる。材料は、全てが市販のもので済ませられるため、たとえ失敗しても大した損失にならないため、気楽に全力で打ち込めるという。
指導教官らの指導原則は、学生たちからの質問があれば、惜しみなく知識を提供するが、質問がなければ静観する。教官らは、学生たちが何度も失敗を重ねてから、彼らに助けを求めて来た時に、初めて助言し、その後は学生たち自身で問題解決できるまで見守っている。これは、学生たちに、自分達で考え、必要ある時のみ指導するという方式で、学生たちを鍛えていくという一種の教育方針である。
大学生たちが独自に研究・開発している超小型人工衛星は、キューブサットと呼ばれる衛星で、重さは10キロ以下で、日本では、2012年からこの衛星の生産が増え始め、多い時には年間300機ほどにのぼる。今年は3月末までにすでに約200機が実際に使用されたという。
この様に市販の電子部品を使った低コストで短期間に開発した超小型衛星は、国際宇宙ステーション(ISS)からも打ち上げることができるようになったことで、利用が飛躍的に広がったのである。
大阪府立大学と室蘭工業大学では今年2月、超小型衛星「ひろがり」を打ち上げた。10センチ角の立方体を二つつなげた形で、太陽電池パネルを模したプラスチック板を宇宙で広げる実験などをおこなったという。宇宙空間に放つのには、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が12年に始めた有償サービスもすでに利用している。この超小型衛星は補給船の荷物としてISSに運び込まれ、滞在中だった野口聡一宇宙飛行士に依頼し、他の超小型7機と一緒に放出された。
しかし、このような超小型衛星の機能には制限が多いという欠点もある。まず、太陽電池を多く積めず、通信にも制約がある。望遠レンズも積むことが出来ず、解像度の高い写真は撮れない。超小型衛星には姿勢制御機能を持たないものが多く、向きも自由には変えられない。
ところで、超小型衛星を研究・教育用に活用する高等研究・教育機関が増えている。大学関係者によると、学生によるこのような超小型衛星の設計から開発、運用まで、すべてを学生自身が自主的に体験できる学び方は、システム工学的な学びかたとしては理想的であると言うのである。
近年、宇宙開発への参入を目指している途上国の中には、日本の大学のこのような教育方式に強い関心をもち、研究生を送り込むようになった。一方、少子高齢化による学生数の減少に悩む日本の地方の大学では、優秀な学生を受け入れることができるという、大学にとって死活問題でもある学生数の確保という“超大型”の効果が生まれるようになったのである。
今どき ニッポン・ウォッチング Vol.218
早氏 芳琴