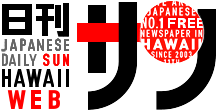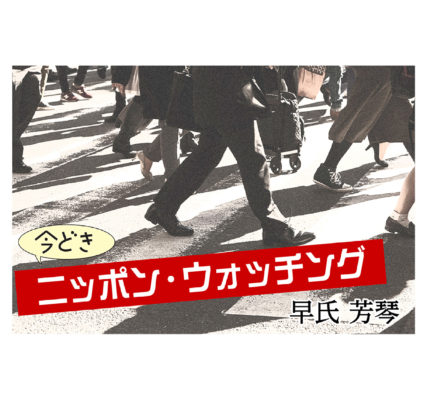感染症を機に 「中華料理」の食文化に変化が?
今回は日本の話から少し離れ、お隣中国の食についてお話ししたい。
中国人の食文化に対する関心と執念深さは、世界中でよく知られている。中国の歴史は五千余年あり、国力は盛衰の変化が激しく、古くは世界一の覇者となり、近代では近隣諸国や西洋列強に抑圧されながら辛うじて今日まで生き延び、その後、特に現代70年足らずの間には、世界第2位の経済・軍事大国として君臨するに至ったのである。
国威が隆盛の時には、諸外国の朝貢特使を迎え入れ、国の最高権力者が自ら來訪者を接見し、盛大な宴会を催して、友好関係を対外的に誇示する。盛大な宴会に見る「山珍海味(山海の珍味)」の豊かさや宴会の進行状態は、国宴の規範として全国に伝わる。そのため、中国料理に見る「大皿料理の伝統文化」は延々と受け継がれてきた。
その特徴は、大きな皿に沢山の料理を盛り付け、宴会参加者が各自の箸で料理をつつき合い、あるいは招待主が料理を客に取ってあげるのが最高の礼儀であるとされてきた。だが、「コロナ禍」の突然の襲来で、今や中国料理のこの伝統的な「おもてなし」の作法は、肯定されるのではなく、むしろ否定的に見なされるようになった。
中国政府の発表によると、国内でのクラスター(集団感染者)の約8割が家庭内で発生したものであると言う。そのため、各地の「中国飯店協会」などの組織は、「料理を事前に取り分けてから客に提供すべき」または「取箸を使用する」と言うように、「分食制」(料理をまず分け合ってから食べる)を実施するようにと、加盟店に呼びかけている。さらに、取箸は各自用の箸と区別がつくよう、文字や記号を刻む工夫も提案された。
中国国営の新華社は、この「分食制」の利点について、食材の浪費を減らすことにもつながるとして、「これは文明化された食生活の再構築に役立つ」との記事を掲載したばかりでなく、中国の歴史書である『史記』には、楚の項羽と漢の劉邦が会談した「鴻門の会」(紀元前206年)の参加者も、料理を先ず分けてから食べる、と記述されていることを紹介し、「中国には『分食制』の歴史は長い」とアピールする程である。
「大皿料理の食事リスク」が指摘されたのは今回が初めてはなかった。実は、2002年に中国で重症急性呼吸器症候群(SARS)が流行った時にも、「分食制」が広く呼びかけられたが、SARSが下火になるや、この運動は瞬く間に忘れられてしまった。歴史や文化の長い国には、それぞれの古い風俗や慣習がある。新しい慣習が、特に古い伝統文化を有している国民に根づくまでには、相当の時間が必要である。中国も例外ではあり得ない。
SARSと「コロナ禍」の“洗礼”をまともに受けてきた中国が、いかにこの難局から教訓を活用し対処すべきであるか、注目するところであろう。
日本は科学技術と医療において先進国の一員と言われる。全世界の人命にかかわる疫病が流行っているこの時期にこそ、中国の貴重な経験と先進的な医療技術によって、この厄災を乗り切るすべを模索して欲しいところである。
今どき ニッポン・ウォッチング Vol.184
早氏 芳琴