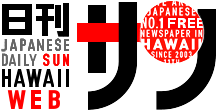今年のノーベル物理学賞に、気候変動予測の基礎を築いた米プリンストン大上席気象研究員、真鍋淑郎さん(90)が選ばれた。真鍋さんは米国籍ではあるけれど、日本の科学者の国際的水準の高さを喜ぶ声が聞かれる。しかし、今後も日本から科学分野でノーベル賞学者が続々と生まれるかというと、現状は過去の実績、遺産に依存した成果との見方が強く、将来の見通しには懸念も大きい。政府は大学の独立法人化を通じて、研究環境を整備するより、大学への交付金を減らす政策を進めてきた経緯があり、研究環境の将来を危ぶむ声が聞かれる。
真鍋さんは何故、日本ではなく米国での研究生活に転身したのか。受賞決定後の記者会見で、日本社会の「同調圧力」を指摘し、「アメリカでは、自分のしたいようにできます。他人がどう感じるかも気にする必要がありません」「自分の使いたいコンピュータをすべて手に入れ、やりたいことを何でもできました」と語った。
また、日本では「好奇心に駆られた研究が少なくなっている。日本の教育をどのように改善するか、考えてほしい」「科学者と政策決定者の双方がコミュニケーションを取っていない。アメリカでは、国立科学アカデミーが政府に非常に効果的な形でアドバイスをしており、はるかにうまくいっている」とも指摘した。率直な言葉から、日本の科学研究現場の課題が浮かび上がる。
科学者と政策決定者のコミュニケーションの課題では、日本学術会議が推薦した学者6人を、安倍政権が理由も明らかにせず任命拒否し、菅義偉政権もこの方針を踏襲、総選挙中に岸田文雄首相も見直しの姿勢を見せなかった。これは日本の政治にとっても、国民にとっても極めて不幸な事態だ。
著書「国家の品格」(2005年)で日本の拝金主義に警鐘を鳴らした数学者、藤原正彦さんの言葉が、真鍋さんの指摘に重なる(毎日新聞10月22日夕刊掲載インタビュー)。「半世紀前は誰も気候変動などに興味を持っていなかった。だから(真鍋さんの研究は)すごいのです。すぐに役に立つうんぬんじゃないところからノーベル賞は生まれる。逆に言えば、3年後やら5年後やらに役立ちそうな研究などに真に独創的なものはないと思ってよい」と藤原さん。
市場経済を優先し金儲けが出来ることを第一の価値観に置いた自民党政権。大学への交付金を減らし、研究の補助金支給も、数年後に役に立つかどうか、が選考基準になる状況では、将来のノーベル賞学者は生まれない。
真鍋さんの受賞決定前に、筆者は気になるニュースを目にしていた。東京大学の藤井輝夫総長は10月1日、今後6年間の「基本方針」を発表し、自主財源確保のため、1千億円程度の基金を創設する計画を明らかにした。2004年の国立大学法人化を機に、交付金減額に対応するため、東大は「東大基金」を創設したが、原資は寄付金のみで、20年度末時点の総額は189億円にとどまる。ここ5年程の寄付額は2016年の約382億円から2020年の約527億円と伸びを見せているが、とても十分とは言えない。
私立大では慶応大が870億円、早稲田大が298億円の基金を持つ。文部科学省のデータだと、米国のハーバード大は4兆5千億円、エール大は3兆3千億円の基金を運用し、研究環境の向上に努めている。
個人的な話になるが、筆者も東大の寄付制度に協力して数年前に規定に従って寄付をした。一定額以上の寄付者の名前は、安田講堂の椅子の背面に取り付けられた銘板などに刻印され、ホームカミングデーなどで安田講堂を訪れるたびに目にすることが出来る。これは寄付を促すための手段でもあるが、善意の寄付だけではなかなか目的達成は難しい。
今回、藤井総長が打ち出した「基金」の対象は、個人的な寄付だけではない。原資として想定されているのは、これまでに大学が投資してきたベンチャー企業の株式売却益や、東大の研究から生まれた知的財産に対して民間企業が負担する使用料などを積み立てるという。
東大に由来するベンチャー企業は400社を超え、企業から得られる研究成果の使用料はこれまでの累計で100億円を超えているという。同郷の大学後輩、前田瑶介さんらが設立したWOTA株式会社は、「水道のない場所で水利用を実現するポータブル水再生プラント」を開発、長野水害などの災害現場でも実績を残している。こうしたベンチャー企業とのコラボが、「基金」の充実につながることが期待されるが、本来は政府がノーベル賞学者を育てる環境を作り上げることが必要ではないか。
基金は、運用益で著名な研究者を招聘することなどが目的で、大学の判断で自由に使える独自財源を増やすことを目指す。しかし使途が決まっていない資金を国立大が長期間ストックできない現行制度を見直す必要があり、文部科学省の対応が課題となる。
自民党は総選挙の公約で「10兆円規模の大学ファンド」の創設を掲げた。この公約が果たして実現するのか、見守りたい。


高尾義彦 (たかお・よしひこ)
1945年、徳島県生まれ。東大文卒。69年毎日新聞入社。社会部在籍が長く、東京本社代表室長、常勤監査役、日本新聞インキ社長など歴任。著書は『陽気なピエロたちー田中角栄幻想の現場検証』『中坊公平の追いつめる』『中坊公平の修羅に入る』など。俳句・雑文集『無償の愛をつぶやくⅠ、Ⅱ、Ⅲ』を自費出版。
(日刊サン 2021.11.03)